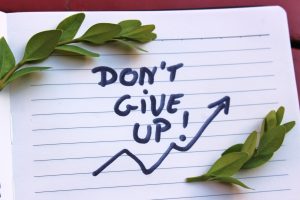経営者保証ガイドラインと第二会社法を活用の再生劇!
【事例】アサヒ運輸の再生劇 - 経営者保証ガイドラインと第二会社法を活用
大阪で長年地域に根ざした運送業を営んできたアサヒ運輸は、近年、経営状況が悪化していました。燃料費の高騰、ドライバー不足、そして追い打ちをかけるようにコロナ禍による物流需要の減少。代表取締役の太田浩二氏は、重苦しい気持ちで日々を過ごしていました。金融機関からの借入金は膨らみ、個人保証をしている浩二氏とその妻である取締役の由紀子氏の肩にのしかかる重圧は、日に日に増していきました。
そんなアサヒ運輸が、どのようにして危機を乗り越え、再生を成し遂げたのか。その軌跡を辿りながら、経営者保証ガイドラインと第二会社法の活用事例を紹介します。
※注記:登場する法人・個人はすべて仮名です。
アサヒ運輸の苦境 - 経営者保証の重圧
アサヒ運輸は、大阪南部に本社を構える、創業40年の歴史を持つ運送会社です。代表取締役の太田浩二氏は、先代である父親から事業を引き継ぎ、長年地域経済に貢献してきました。主力事業は、地域内の食品配送と、関東方面への長距離輸送でした。しかし、近年は燃料費の高騰やドライバー不足、そしてコロナ禍の影響による物流需要の減少という三重苦に見舞われ、業績は悪化の一途を辿っていました。
アサヒ運輸は、事業を継続するために、メインバンクであるあかつき信用金庫から多額の融資を受けていました。その際、浩二氏と由紀子氏の二名は、個人保証を提供していました。これは、会社が倒産した場合、個人資産で借金を返済しなければならないことを意味します。浩二氏は、会社の将来だけでなく、家族の生活を守るためにも、必死に事業を立て直そうと努力していました。コスト削減や業務効率化に取り組み、新規顧客の開拓にも奔走しましたが、状況は好転するどころか、資金繰りは日に日に厳しくなっていきました。
M&Aコンサルタントとの出会い - 一筋の光
そんな八方塞がりの状況の中、浩二氏は、以前から懇意にしていたM&Aコンサルタントの佐藤氏に相談を持ちかけました。「このままでは、会社も家族も守れないかもしれない…」浩二氏は、不安な気持ちを吐露しました。佐藤氏は、浩二氏の話をじっくりと聞いた後、真剣な表情で言いました。「太田さん、まだ諦めるのは早いです。再生の道は必ずあります。」
佐藤氏は、アサヒ運輸の現状を詳しく分析し、「経営者保証に関するガイドライン」と「第二会社法」という制度を活用した再生計画を提案しました。浩二氏は、これらの制度について詳しく知らなかったため、佐藤氏から詳しい説明を受けました。
経営者保証ガイドラインと第二会社法 - 再生の道筋
1. 経営者保証に関するガイドライン
「経営者保証に関するガイドライン」は、金融機関に対し、経営者保証に過度に依存することなく、企業の実態に応じた融資判断を行うよう促すものです。ガイドラインでは、以下の3つの要件を満たす場合には、原則として経営者保証を求めないこととしています。
- 法人と経営者の明確な分離:資産の所有やお金のやり取りに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されていること。
- 財務基盤の強化:財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能であること。
- 適切な情報開示:金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されていること。
佐藤氏は、アサヒ運輸がこれらの要件を満たすためには、財務状況の改善、情報開示の体制整備、そして、弁護士のサポートが必要だと説明しました。
経営者保証ガイドラインに基づく手続き
佐藤氏は、早速、アサヒ運輸のメインバンクであるあかつき信用金庫に連絡を取り、経営者保証ガイドラインに基づく手続きを進めることを伝えました。信用金庫側は、アサヒ運輸の現状を把握しており、ガイドラインの活用には前向きな姿勢を示しました。
佐藤氏と浩二氏は、信用金庫の担当者と面会し、アサヒ運輸の再生計画を説明しました。具体的には、第二会社法を活用して長距離輸送部門を日の丸トランスポートに譲渡すること、残った小口配送部門は縮小し、最終的には会社を清算すること、そして、浩二氏は日の丸トランスポートに再就職し、債務返済に協力していくことを説明しました。
信用金庫側は、アサヒ運輸の再生計画を評価し、経営者保証ガイドラインの活用を認めました。これにより、浩二氏と由紀子氏は、個人保証の重圧から解放され、再スタートを切ることができるようになりました。浩二氏は、安堵の表情で、佐藤氏と田中先生に感謝の言葉を述べました。「本当にありがとうございます。これで、安心して事業再生に専念できます。」
弁護士との相談
佐藤氏に紹介された弁護士の田中先生は、事業再生に精通していました。田中先生は、浩二氏と由紀子氏に、経営者保証ガイドラインの活用と第二会社法による再生について、分かりやすく説明しました。「ガイドラインを活用することで、個人保証から解放され、再スタートを切ることができます。第二会社法を活用すれば、事業を承継する新会社を設立し、旧会社の債務を整理することができます。」田中先生の言葉に、浩二氏と由紀子氏は、希望の光を見出しました。
2. 第二会社法
第二会社法とは、事業を承継する新会社を設立し、旧会社の事業を新会社に譲渡することで、旧会社の債務を整理する制度です。新会社は、旧会社の事業を引き継ぎながら、債務を負うことなく、新たなスタートを切ることができます。
佐藤氏は、アサヒ運輸の長距離輸送部門を承継する新会社「株式会社ニューアサヒ運輸」を設立し、旧会社の事業を新会社に譲渡することを提案しました。譲渡先としては、以前から取引があり、アサヒ運輸の事業内容をよく理解している日の丸トランスポート株式会社が最適だと考え、佐藤氏は日の丸トランスポートとの交渉も進めました。日の丸トランスポートは、アサヒ運輸の長距離輸送部門の事業価値を高く評価し、従業員も引き継ぐことを条件に事業譲渡を受け入れました。
これにより、旧アサヒ運輸の債務は旧会社に残され、新会社は健全な財務状態で事業をスタートすることができました。また、浩二氏は日の丸トランスポートの長距離輸送部門の責任者として、引き続き事業に携わることができました。長距離輸送部門の従業員も、日の丸トランスポートに転籍し、雇用が維持されました。
事業譲渡後のアサヒ運輸 - 破産手続き
長距離輸送部門を日の丸トランスポートに譲渡した後のアサヒ運輸は、地域内の小口配送部門のみとなり、残ったわずかな資産と多額の負債を抱えていました。田中先生は、債務の整理のため、裁判所に破産を申し立てる手続きを進めました。
破産手続きでは、裁判所が選任した破産管財人が、アサヒ運輸の資産を管理・処分し、債権者に配当します。浩二氏は、破産管財人に対して、会社の財務状況や事業の経緯について説明し、必要な資料を提出しました。また、債権者集会にも出席し、債権者に対して状況を説明し、謝罪しました。
アサヒ運輸の資産は、車両や事務所 equipment など、限られたものでした。破産管財人は、これらの資産を売却し、債権者に配当しましたが、債務を全額弁済することはできませんでした。しかし、浩二氏と由紀子氏は、経営者保証ガイドラインの活用により、個人保証を解除していたため、私財を犠牲にすることなく、新たな生活を始めることができました。
破産手続き後の太田浩二氏と由紀子氏
アサヒ運輸の破産手続き後、浩二氏は、日の丸トランスポートの長距離輸送部門の責任者として、精力的に働いています。長年培ってきた経験と知識を活かし、部門の業績向上に貢献しています。また、由紀子氏は、新たな仕事を見つけ、家計を支えています。二人の生活は、以前ほど裕福ではありませんが、家族で協力し合いながら、前向きに生きています。
浩二氏は、今回の経験を通して、経営者保証のリスクと、事業再生の難しさを痛感したと言います。しかし、同時に、経営者保証ガイドラインや第二会社法といった制度を活用することで、再起の道が開けることも学びました。浩二氏は、自身の経験を活かし、今後、同じような悩みを抱える経営者の支援をしていきたいと考えています。
アサヒ運輸の再生 - 具体的な取り組み
アサヒ運輸は、再生に向けて、以下のような具体的な取り組みを行いました。
1. 財務状況の改善
- 不採算事業の見直し
- コスト削減(車両の維持費、事務所経費など)
- 資金繰り管理の徹底(資金繰り表の作成、毎月の収支分析など)
2. 情報開示の徹底
- 財務諸表の作成(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)
- 事業計画書の作成(今後の事業展開、収益見通しなど)
- 信用金庫への定期的な報告(月次決算、経営状況の説明など)
3. 従業員との協力
- 現状と再生計画の説明会の実施
- 意見交換会の開催
- 従業員提案制度の導入
4. 専門家との連携
- M&Aコンサルタント、弁護士、税理士との連携
- 金融機関との交渉を専門家に依頼
- 再生計画の実行を専門家にサポート
5. 日の丸トランスポートとの交渉
- 事業譲渡の条件交渉
- 従業員の雇用維持の交渉
- 譲渡価格の交渉
6. 債権者との交渉(破産手続き前)
- 破産手続きの説明
- 債権者への謝罪と理解を求める
まとめ
アサヒ運輸の事例は、経営者保証ガイドラインと第二会社法を活用することで、経営危機を乗り越え、再生を成し遂げることができることを示しています。すべての債務を弁済し、会社を存続させることが再生の唯一の道ではありません。場合によっては、会社を清算し、新たなスタートを切ることも、再生の一つの形と言えるでしょう。
資金繰りに悩む経営者の方は、諦めずに、専門家のサポートを受けながら、自身にとって最善の再生への道を模索しましょう。
※注記:登場する法人・個人はすべて仮名です。